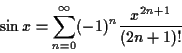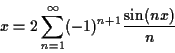|
ファイル名 cond1.rr
1: def main(A,B) {
2: print(A+B);
3: print("A kakeru B=",0);
4: print(A*B);
5: }
6: end$
実行例
[0] load("cond1.rr");
[1] main(43,900)$
943
A kakeru B=38700
|
|
左のプログラムはあたらえられた二つの数の和と積を出力するプログラムである.
関数の引数として数 A, B を読み込む.
2, 3 行目で和と積を計算して出力する.
{ と } かこんだものが
ひとかたまりの単位である.
実行は自前の関数 main() に数字をいれて評価すればよい.
字さげ(インデントという)をしてわかりやすく書いていることに注意.
なお,
cond1.rr のロードが失敗する場合は,
|